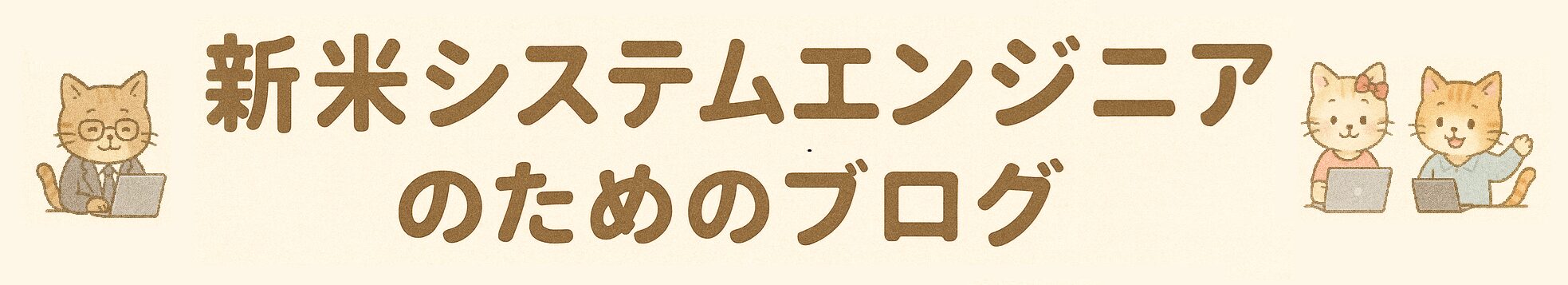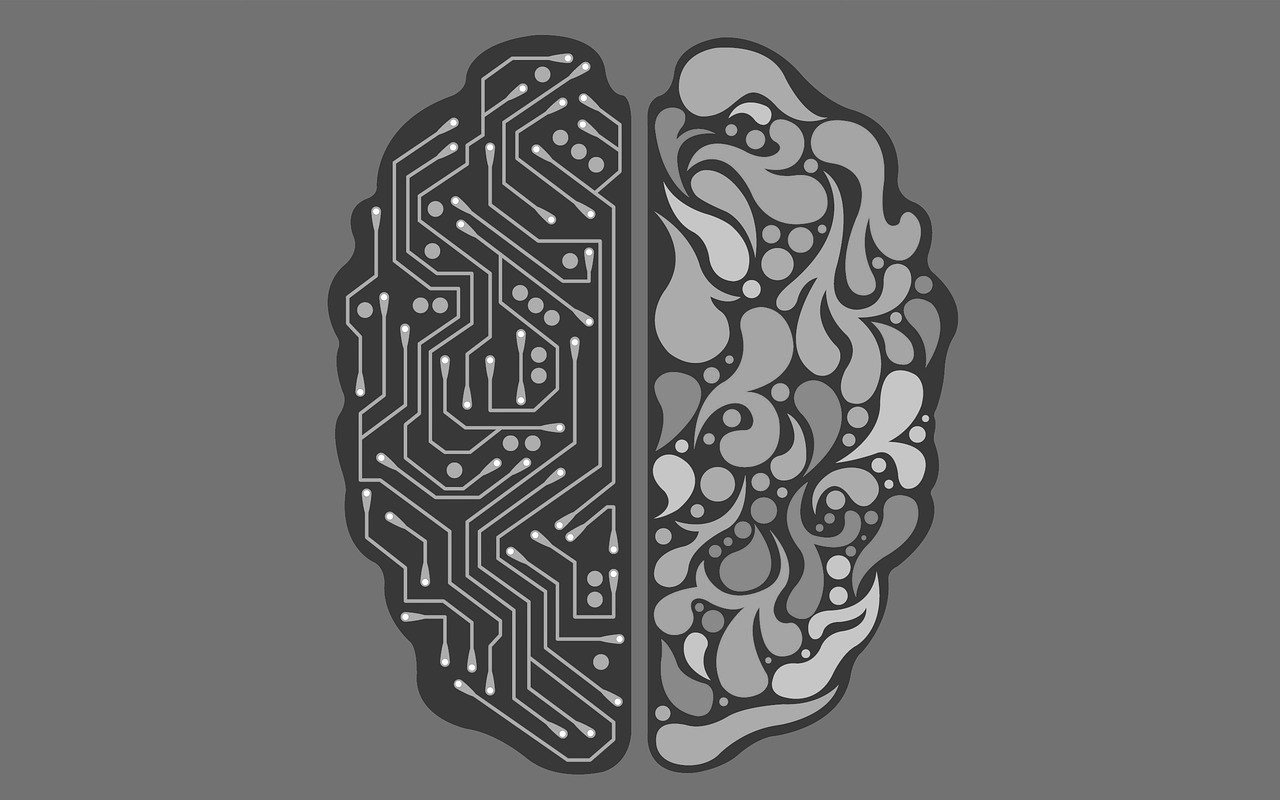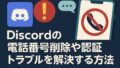アイキャッチ画像: © 2017 Seanbatty Pixabay
「生成AIを業務で活用したいけど、情報漏えいや法規制のリスクが怖い…」
年々進化するAI。
使えないとビジネスについていけないのは分かっていても、多くの企業が最初につまづくポイントになっています。
まずは、生成AIのリスクは正しく理解し、事例やガイドラインを参考にすることで、個人情報を守りながら企業として安全に活用する方法が見えてきます。
この記事では、生成AIのリスクを具体的な事例や最新ガイドラインとともに解説し、企業が取るべき個人情報保護や対策のポイントを3つご紹介したいと思います。
生成AIのリスクとは?基本知識と現状を押さえよう

画像: © 2016 lil_foot_ Pixabay
生成AIとは何か|注目される背景と利用シーン
生成AIとは、人が書くような文章や画像、音声などを自動で作り出す技術です。
例えばChatGPTのように文章の質問に答えたり、画像を作成するツールがあります。
今では業務での利用も広がり、レポート作成や顧客対応、企画のアイデア出しなど様々な場面において、業務を短時間で終わらせられる点が注目され、多くの企業が関心を寄せています。
しかし便利さの裏側には、思わぬリスクも潜んでいるのです。
生成AIのリスクが問題視される理由
生成AIには、いくつかのリスクがあります。代表的なものは以下のとおりです。
- 情報漏えいのリスク
AIに入力した情報が、学習データとして使われる可能性があり、他のユーザーに漏れる恐れがあります。 - 誤情報(ハルシネーション)のリスク
AIは自信たっぷりに間違った情報を作り出すことがあります。表面的には正しく見えるため、誤情報に気づきにくい点が危険です。 - 著作権侵害のリスク
AIが既存の著作物に似たコンテンツを作り出すことで、法的トラブルになることがあります。
これらのリスクが問題視されるのは、AIの進化が非常に速く、法律やルールが追いついていないためです。
その結果、どこまでが許される利用なのかがはっきりせず、企業や個人が安心して使えない状況になっています。
例えば、著作権の問題ひとつを取っても、「どこまで似ていれば侵害になるのか」という基準が明確でないため、AIを使う企業が自分たちでリスクを判断しなければなりません。
また、情報漏えいのリスクについても法律の整備が遅れているため、万が一漏えいが起きた場合の責任範囲や対応がはっきりせず、企業にとって大きな不安要素となっています。
つまり、法律やルールが未整備の状態では、AIの便利さを安心して活用できず、企業が二の足を踏む原因になっているのです。
生成AI活用のメリットとリスクのバランス
生成AIには、非常に大きなメリットがあります。例えば以下のような点です。
- 業務の効率化
文書作成やデータのまとめなど、これまで時間がかかっていた作業を短時間で終わらせることができます。 - アイデア創出の支援
新しい企画や提案のヒントを短時間で多数出せるため、発想の幅が広がります。
しかし、一方で以下のようなリスクも無視できません。
- 誤情報をそのまま使ってしまう危険
AIの回答には間違いが含まれる可能性があり、それを信じて社外に出すと大きな問題になります。 - 機密情報が漏れる恐れ
AIに入力した内容が学習に使われ、外部に漏れる可能性があります。
つまり、生成AIは非常に便利ですが、「速さ」と「便利さ」を求めるあまり、誤情報や情報漏えいという大きなリスクを抱える点が問題です。
企業が活用する際には、便利さを享受しつつ、リスクを最小限に抑える取り組みが求められます。
生成AIに潜む具体的リスク事例とその背景

画像: © 2017 madartzgraphics Pixabay
個人情報漏えいのリスク事例
生成AIを業務で利用する際は、個人情報漏えいのリスクに対して十分な注意が必要です。
なぜなら、AIに入力した機密情報や個人情報が、学習データとして蓄積され、思わぬ形で他のユーザーに漏洩する可能性があるからです。
近年では、個人情報の漏洩が多額の損害賠償につながる恐れもあり、決して無視できる問題ではありません。
実際、2023年にはSamsung(サムスン)のエンジニアがChatGPTに自社のソースコードを入力した結果、機密情報が流出するリスクが問題視され、同社は社内でChatGPTなどの利用を禁止する事態となりました。
出典:https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak
こうしたリスクを避けるためにも、企業ではAIサービスの利用規約に「入力されたデータを学習に使用する」などの文言がないことを確認したり、社内規定を整備・周知することが不可欠となります。
【個人情報漏えいリスクのポイント】
- 入力情報がAIの学習に使用される可能性があります。
- 利用規約(例:「入力されたデータを学習に使用する」)の確認が必須です。
- 企業は社内規定を整備し、徹底的な周知が必要です。
著作権や知的財産権の侵害リスク
生成AIの活用には、著作権や知的財産権の侵害リスクへの注意も必要となります。
その理由は、AIが生成するコンテンツは既存の著作物と酷似してしまう場合があり、著作権侵害として訴訟などの法的トラブルに発展する可能性があるからです。
例えば、2023年にはGetty ImagesがStability AIを提訴しました。
Gettyの写真約1,200万点が無断で学習に使われ、生成された画像に同社のウォーターマークが含まれていたことも争点となりました。
出典:https://gigazine.net/news/20230207-getty-sues-stability-ai/
このようなリスクを回避するためにも、生成AIを利用する前に著作権やライセンス状況を必ず確認することが重要です。
【著作権侵害リスクのポイント】
- 生成物が他人の著作物に酷似する可能性があります。
- 訴訟・法的トラブルに発展するケースがあります。
- 利用前に著作権やライセンス状況の確認が重要です。
ハルシネーション(誤情報生成)のリスク
最近の高度な生成AIでは減ってきましたが、ハルシネーション(誤情報の生成)のリスクも考慮しておきましょう。
というのも、生成AIの性能が年々上がっているとはいえ、事実とは異なる情報をもっともらしく出力する(=嘘をつく)可能性は残っているからです。
実際に、2023年には米国で弁護士がChatGPTを使って作成した裁判資料に、存在しない判例が記載されていたことが発覚し、裁判所から合計5,000ドルの罰金を科されるという事例が起きました。
出典:https://openlegalcommunity.com/fake-case-lawyers-get-sanctioned/
虚偽の情報を提示してしまうことは発信者の信用を大きく下げ、最悪は処罰の対象となることもあります。
そのようなリスクを回避するためにも、生成AIの出力内容をそのまま鵜呑みにせず、必ず事実確認を行うことが重要です。
【ハルシネーションのリスクポイント】
- AIはあるべき物語を「もっともらしく」生成することがあります。
- 誤情報の社外流出は信頼損失や法的問題につながります。
- 最終的には人が裏取りし、精査する必要があります。
生成AI活用における最新ガイドラインと法規制の動向

画像: © 2015 succo Pixabay
日本国内の最新ガイドライン動向
生成AIの活用が広がるなか、日本でも企業向けのガイドラインが次々と発表されています。
現状、日本国内ではまだ法律として明確に規制する段階には至っていないものの、自主的なルール作りが求められているという状況です。
2024年には、経済産業省が「AI事業者ガイドライン」を公表しました。
この中では、個人情報や機密情報を安易に入力しないこと、AIの回答を必ず確認することなど、基本的な利用上の注意がまとめられています。
また、個人情報保護委員会も生成AIに関する声明を出し、AIに個人情報を入力する際のリスクや取り扱いについて企業に注意喚起を行いました。
出典:https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230623003/20230623003.html
【日本国内のガイドライン動向ポイント】
- 法律は未整備だが、各省庁がガイドラインを提示しています。
- 企業自身がポリシーを定め、運用ルールを徹底する必要があります。
- 個人情報の取り扱いに関する注意が特に強調されています。
#装備品等の研究開発における責任あるAI適用ガイドライン を公表しました。令和6年7月に策定・公表した防衛省AI活用推進基本方針を受け、防衛省の装備品等の研究開発における責任あるAI適用のコンセプトを示した防衛省・自衛隊独自のガイドラインです。
詳細はこちら→https://t.co/s55JhdLSh1 pic.twitter.com/oUmr9Rxj4B— 防衛装備庁 (@atla_kouhou_jp) June 6, 2025
EUをはじめとする海外の規制トレンド
海外、特にEUでは生成AIを含むAI全般の規制が本格的に進んでいます。
EUは世界の中でも最も厳格なAI規制を導入しようとしており、リスクが高い=社会的影響度が大きい使い方になるほど、厳しいルールを適用するものとなっています。
例えば、医療や金融などで使われるAIは「高リスク」とみなされ、厳格な透明性の確保や説明責任が求められることになります。
また、生成AIについても、出典の明示や著作権保護など、クリエイティブ領域での規制が盛り込まれています。
2025年施行を目指して動いており、今後日本企業にも影響が及ぶ可能性は高いでしょう。
出典:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682
【海外の規制トレンドのポイント】
- EUはAI規制を世界で最も厳しく整備しつつあります。
- 生成AIにも透明性や説明責任が課される方向です。
- 日本企業も海外展開するなら無視できません。
業種別に異なる法的リスクと留意点
生成AIのリスクや規制は、実は業種によって大きく異なり、同じAIでも使う業界によって許される範囲や規制の厳しさが全く違います。
例えば、金融業界ではAIが誤情報を出すことが投資判断に直結するため、特に厳しい規制が課せられています。
2023年には金融庁が、生成AI利用に際して「誤情報の排除」や「顧客説明責任の徹底」を強調する方針を示しました。
出典:https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250304/aidp.html
また医療分野では、患者情報という非常にセンシティブなデータを扱うため、AI活用には厚生労働省のガイドラインを厳守する必要があります。
生成AIによる診断支援やカルテ作成が注目されていますが、誤診リスクや個人情報漏えいの問題が懸念されています。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001310044.pdf
すでにどの業界でも「生成AIは利用して当たり前」のものになっています。各業界団体のガイドラインや規則をしっかり確認しておきましょう。
【業種別リスクのポイント】
- 金融業界は誤情報排除が特に重要です。
- 医療分野では個人情報保護と誤診リスクに厳格対応が必要です。
- 各業界のガイドラインを把握し、遵守することが必須となります。
企業が取るべき生成AIリスク対策|個人情報保護と安全活用の3つのポイント

画像: © 2014 steinchen Pixabay
社内規定・ポリシーの整備
生成AIを安全に使うために、まず企業がやるべきことは 社内規定の整備です。
生成AIは非常に便利ですが、取り扱いを誤ると情報漏えいや法的トラブルを招きかねません。
三井住友銀行では「責任あるAIポリシー」を策定し、AI利用の方針を整備しています。
出典:https://www.smbc.co.jp/ai_policy/
こうした取り組みは、社員が安心してAIを活用するための大きな土台となります。
システム面でのリスク管理
規定を作るだけではリスクは防ぎきれません。
システム面での対策 も不可欠です。
例えばマイクロソフトの「Azure OpenAI Service」では、入力データを外部に送信しない設定が可能で、アクセス制御や操作履歴の管理機能も備えています。
出典:https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/cognitive-services/openai/overview
こうした技術的な制御を加えることで、うっかり機密情報を入力してしまった場合でも、被害を最小限に抑えることができます。
教育と啓発によるヒューマンエラー防止
どんなに仕組みを整えても、最終的にAIを使うのは人です。
だからこそ 教育と啓発 が重要です。
サムスンでは、社内機密をChatGPTに入力してしまった事例が問題となり、社内で生成AIの使用が全面禁止されました。
出典:https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak
このように、社員の意識次第でリスクが大きく変わるのです。
過去のトラブル事例を使った研修やケーススタディは、リスクを自分ごととして理解させるうえで非常に有効です。
企業が取るべき生成AIリスク対策まとめ
以下に、企業が実践すべき生成AIリスク対策のポイントをまとめました。
| 対策項目 | 内容 |
| 社内規定の整備 | 入力禁止情報を明文化し、AI出力は人が必ず確認するルールを徹底 |
| システム管理 | ログ管理、アクセス制御、機密情報検知などの技術的対策を導入 |
| 教育・啓発 | 社員研修や過去事例の共有でヒューマンエラーを防止 |
生成AIリスク対策に関するよくあるQ&A

画像: © 2016 loufre Pixabay
よくある疑問とその回答例
個人利用と業務利用でルールは違うのか?
はい。業務利用では、個人利用よりはるかに厳しい運用ルールが必要です。
個人と比べ、業務では顧客情報や企業の機密を扱うため社会的な影響が大きく、情報漏えいや著作権違反が即座に損害賠償につながります。
例えば、業務で生成AIを使うときは、入力する情報を精査し、AIの回答をそのまま外部に出さないよう、人が必ず確認するルールを設けることが大切です。
こうした体制を整えることで、万一のトラブルを防ぎやすくなります。
AIに入力した情報は外に漏れるのか?
可能性はゼロではありません。
多くのAIサービスでは、入力されたデータを学習に活用する場合があり、その旨が利用規約に明記されています。
企業が機密情報を入力した場合、その情報が将来的にAIの回答の中で再利用される恐れもあります。
こうしたリスクを避けるためには、利用規約を必ず確認し、機密性の高い情報は入力しないことが重要です。
AIの回答はどれくらい正確なのか?
AIの回答には誤りが含まれることがあり、そのまま信じて使うのは非常に危険です。
生成AIは自信たっぷりに誤った情報を作り出すことがあり、これを「ハルシネーション」と呼びます。
特に専門分野では、正確かどうかを判断するのが難しい場合もあります。
AIの出力を利用する際は必ず人が裏取りを行い、内容を精査することが大切です。
生成AIのセキュリティ活用とサービスの選び方

画像: © 2022 tungnguyen0905 Pixabay
生成AIを安全に活用するためのポイント
生成AIを安心して活用するために、ポイントから押さえていきましょう。
というのも、過度にリスクを恐れて手を出さない企業も多いですが、まずポイントを理解しておけば対応できることがたくさんあるからです。
また、細かい運用のルールは、実際に使う中で見えてくることが多く、運用を重ねて「やり方のコツ」を積み上げることが、本当の安心につながります。
【生成AIを安全に使うためのポイント】
- 機密情報や個人情報を入力しないルールを徹底します。
- AIが出した内容は必ず人が確認します。
- 利用するAIサービスの規約をよく読むことが必要です。
- 自社の利用範囲やリスクに応じた運用ポリシーを作る必要があります。
ポイントを押さえて最低限の安全を確保しつつ、知識や経験を積み重ねてさらに安全を強化していきましょう。
セキュリティサービスの比較と選び方
生成AIの進化は早く、またセキュリティ技術も日進月歩です。
現実問題として自社だけでこの進歩についていくのは困難であるため、常に最新の環境を提供してくれる外部サービスを利用するのが一般的となっています。
大手クラウドサービスは強力な対策を用意しており、中小企業向けの手頃な選択肢も増えていますが、自社の規模やリスクに合ったサービスを選ぶことが重要となってきます。
その理由は、生成AIはあくまで「効率化のためのツール」であり、また、本格的に利用しようとすると、決して安い投資ではないためです。
何も考えずに必要とされないレベルのサービスにしてしまうと「高価なわりに効果がない」という結果になってしまいかねません。
以下に、代表的なサービスとチェックポイントをまとめます。
| サービス名 | 特徴 | チェックポイント |
| Azure OpenAI Service | 入力データを学習に利用しない設定が可能、高度なアクセス管理機能あり | 外部学習利用の有無、ログ管理機能の確認 |
| Vertex AI (Google Cloud) | 自社環境での運用が可能で、データ管理の自由度が高い。 | 海外規制対応、初期コストの比較 |
| ChatGPT Enterprise | 商用利用向けで、入力内容の学習不使用を明言。高いプライバシー保護あり | 学習利用ポリシー、利用規約の確認 |
各サービスとも基本的なポイントは押さえつつ、どのような使い方をするかによって得意、不得意があります。
自分たちがどのような使い方をするのかをしっかりとイメージした上で、各サービスを調べる、サポートに話しを聞いてみるなどしてみることをオススメします。
まとめ:安心して生成AIを活かすために、いま大切なこと

画像: © 2022 Fotorech Pixabay
生成AIは業務の効率化や新たな発想を生む強力なツールですが、情報漏えいや誤情報、著作権問題などのリスクも無視できません。
法規制は整備途上であり、企業は自らポリシーや社内規定を整え、システム面の対策や社員教育を徹底することが求められます。
これからは「使わない」のではなく、「どう安全に使うか」が企業の成長を左右する時代です。
焦らず、一歩ずつ。安心を確保しながら、生成AIの可能性を一緒に広げていきましょう。